2024年4月に新しく出発した研究室です。2024年度後期から学部生の配属が開始され、日々活気ある議論が行われています。
教授: 水原 啓暁 email: mizuhara[at mark]ics.nara-wu.ac.jp
- 大学院生:
- 博士後期課程
- 樋田 智美(社会人)
- 学部4回生:
- 石川 遥菜
- 甲斐 美朱
- 川口 紗矢
- 辻村 瑞希
- 平野 さくら
- 山路 真凜
- 学部3回生:
- 齋藤 朱莉
- 坂上 七彩
- 當麻 佳子
- 新田 桃佳
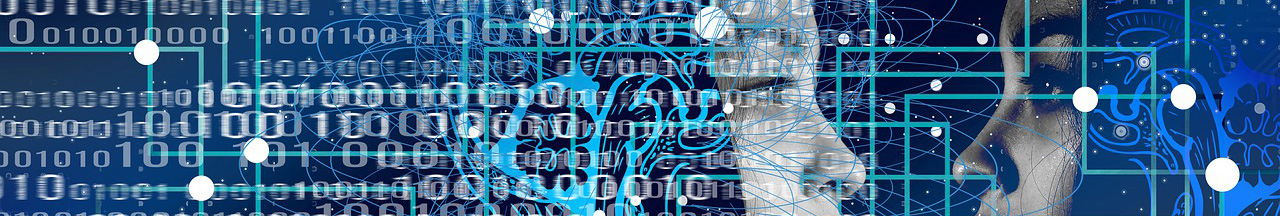
2024年4月に新しく出発した研究室です。2024年度後期から学部生の配属が開始され、日々活気ある議論が行われています。
教授: 水原 啓暁 email: mizuhara[at mark]ics.nara-wu.ac.jp
■ 研究室の特長
当研究室では、脳科学 × データサイエンス を融合させ、未来の社会を変えるような研究を行っています。テーマは「AI」「ブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)」「メタバース」「脳計測」など。世界レベルの研究に挑戦しながら、基礎からしっかり学べる環境を整えています。
■ 学べるスキル
■ 対象となる方
■ 教育体制
進学希望の方は、まずはお気軽にメールでご相談ください(mizuhara[at mark]ics.nara-wu.ac.jp)。
小野島 隆之(滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 助教)
アラル須本 ケンザ 宝(兵庫県立大学 国際商経学部 准教授)